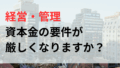在留資格「特定活動」(ワーキング・ホリデー)で日本に在留する外国人が就労目的の在留資格への変更を検討する際における、法的根拠、国際協定上の制約、手続上の要件について、専門的かつ客観的な視点から詳細に解説いたします。
ワーキング・ホリデー制度の目的と法的性質
ワーキング・ホリデー制度は、日本と協定を締結した国・地域との間で、青少年の国際的な交流と相互理解を促進することを主たる目的としています。この制度は、協定国の若者が休暇を利用して相手国の文化や生活様式を体験するための機会を提供するものであり、滞在期間は最長1年と一定の期間が定められています。
この制度では、旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めています。しかも留学生等のアルバイトとは異なり週28時間等の就労時間の制限がありません。ただし、風営法で定められる業種に従事することはできず、労働法上の制限はもちろん生じます。
就労時間の制限ないとはいえ、文化交流を目的とするという制度趣旨からすると、あくまでも一定期間の文化交流活動の一環としての付随的な就労を認めるにすぎません。したがって、就労を前提とした他の在留資格とは明確に区別されます。後ほど記載しますが、この一定期間の滞在という性質が在留資格変更の審査に際して重要な判断基準となります。
在留資格変更の法的根拠と審査基準の考察
日本の出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)20条1項は、在留する外国人が在留資格の変更を希望する場合に、その変更が許可される可能性を定めています。しかし、この条文は無条件の変更を認めるものではなく、「変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されると明記されています(同条3項)。
なお、同条3項但書において、「短期滞在」の在留資格をもって在留する者の申請は「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可しないものとされています。これは、短期滞在という旅行等で用いられることが想定されている簡便な手続きで取得可能な在留資格から、より厳格な審査を必要とする例えば就労可能な在留資格への変更申請を可能としてしまうと制度の趣旨を逸脱する可能性があるためです。
ワーキング・ホリデーは「特定活動」の在留資格によるものであり、「短期滞在」ではないため、この規定を直接適用されることはないと考えられます。しかし、ワーキング・ホリデーが比較的簡便な手続きで取得可能な在留資格であることから、就労を前提とする在留資格への変更申請がその制度の趣旨を逸脱する可能性があるという点では同じ考慮が働き、厳格な審査対象となる可能性が非常に高いといえます。また、ワーキング・ホリデーが1年程度で帰国することを前提とした制度である点も別の在留資格への変更が厳格に審査される一因と考えられます。入国管理局は、申請者が制度を本来の目的外で利用しているのではないかを慎重に判断します。
具体的には、在留資格変更の理由が偶然かつ具体的な就労機会に恵まれた結果であるかどうか、例えば、ワーキング・ホリデー中に日本の企業でアルバイトを経験し、その職務遂行能力が評価されて正規雇用をオファーされたといった場合であれば、申請理由に一定の合理性が認められると考えられます。逆に、最初から就職活動を目的としてワーキング・ホリデー制度を利用していたと判断されるような場合は変更申請が不許可となる可能性があります。
また、当然ながら、変更を希望する在留資格に定められた要件、就労のための在留資格であれば学歴、職務経験、業務内容などの要件をすべて満たしているかが審査されます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、専攻分野と業務内容の関連性、雇用契約などの要件が必要となるのは言うまでもありません。
国際協定における在留資格変更の取り扱い
ワーキング・ホリデーからの在留資格変更の可否を判断する上で、最も重要な要素は、日本と各協定国・地域との間で交わされた口上書、協定、協力覚書などと呼ばれる二国間の合意の内容です。これらの文書は、法的判断の前提となる特別な取り決めであり、在留資格変更の可否を決定づける法的根拠になるといえます。
在留資格の変更が可能となりうる根拠として、一部の国との協定や覚書には、ワーキング・ホリデー滞在者が他の在留資格へ変更することを明示的に禁止する規定が存在しない点が考えられます。この場合、入管法20条1項の原則に基づき、在留資格変更許可申請を行うことが可能と考えられます。これは、協定の文言に変更禁止の規定がない以上、入管法が定める一般的な在留資格変更の考え方が適用されるという解釈に基づいています。
一方、変更が原則として認められないケースとして、多くの国との協定には、「滞在期間中に滞在資格を変更することは認められない」と規定されています。この規定は、ワーキング・ホリデー制度が就労ビザ取得の迂回ルートとして利用されることを防ぐために設けられています。
当該規定が適用される国籍の外国人が在留資格変更を申請した場合、たとえ日本の企業から雇用オファーを受けていたとしても、協定上の制約により申請は不許可となると考えられます。この場合、当該外国人は一度日本を出国し、改めて就労目的の在留資格(在留資格認定証明書交付申請)を申請する必要があります。
各国との協定を確認してみましょう
外務省のウェブサイトには、締結された協定が掲載されています。ワーキング・ホリデーに関する協定も掲載されており、誰でもみることができます。「ワーキング・ホリデー」等の検索ワードで調べてみると、各国との協定が一覧として表示され、それぞれの内容を確認することができます。
オーストラリア、ニュー・ジーランド、カナダ、ドイツ、韓国
これらの国との協定、「口上書」、「協定」、「協定覚書」等名称は様々ですが、これを確認すると、ワーキング・ホリデーによる滞在の期限後の延長や変更について規定されているものがあります。オーストラリアは当局の裁量によるとされ、ニュー・ジーランドとカナダは6か月まで延長を認める可能性を示唆しており、ドイツと韓国は変更や延長について明示的には規定していません。それ以外の多くの国との協定等には変更を認めないとする明確な規定が設けられています。
このような観点から、上記5か国については滞在を継続したまま在留資格の変更が可能であると解釈されています。ただし、前述のとおり、もともと変更を予定していない在留資格であることを考慮すると厳格に審査されることを想定しておくべきでしょう。
在留資格変更手続に関する実務上の留意事項
在留資格変更許可申請は、申請者本人と雇用予定の企業の双方が連携して手続きを進める必要があります。
申請者本人には、在留資格変更を見据える場合、日本語能力の向上や専門スキルの習得など、就労を目的とする在留資格の要件を満たすための自己研鑽が求められます。自身が希望する職種や業務内容が、取得を目指す在留資格の要件に合致するかどうか、客観的に自己評価することが不可欠です。
また、在留資格変更許可申請には、通常、申請から許可まで1〜3ヶ月程度の期間を要します。ワーキング・ホリデーの在留期限が満了する数ヶ月前に、就職活動と申請準備を開始することが不可欠です。期限ぎりぎりの申請は、審査期間中の在留期間満了による不法滞在のリスクを高めます。
一方、企業側には、採用計画の策定が求められます。 ワーキング・ホリデー滞在者を雇用する企業は、在留資格変更手続きにかかる期間を考慮し、採用から入社までのスケジュールに余裕を持たせる必要があります。また、内定後すぐに申請手続きを開始できるよう、あらかじめ必要な書類を確認しておくことが重要です。
企業は在留資格変更許可申請に必要な書類(履歴事項全部証明書、直近年度の決算報告書、会社案内、雇用契約書、採用理由書等)を漏れなく準備しなければなりません。特に採用理由書は、申請者が担当する業務の専門性、なぜその外国人でなければならないのかを具体的に記述し、入国管理局に対して説得力のある説明を行う上で極めて重要な書類です。
また、在留資格の変更は不確実なものであることを想定する必要があります。したがって、不許可となった場合、採用計画に遅延や変更が生じる可能性があることを認識しておく必要があります。企業は、万一にも不許可となった場合の代替案(例:申請者が本国に戻ってから在留資格認定証明書交付申請を行う、結果として申請人の稼働が数か月遅れることがある等)を事前に検討しておくことが大切です。
まとめと専門家への相談
ワーキング・ホリデーからの在留資格変更は、国際協定の規定によってその可否が大きく左右されます。まずはどの国籍なのかしっかり確認しましょう。また、変更が可能とされる国籍の場合でも入管法上の厳格な審査基準を満たす必要があり、個別の状況に応じた判断が求められることを意識しておきましょう。
在留資格の手続を円滑に進め、不許可のリスクを最小限に抑えるためには、最新の法令や協定に精通した専門家(行政書士等)に相談することが最も確実な方法です。専門家は、個々のケースに応じた適切なアドバイス、必要書類の確認、申請手続の代行を通じて成功率を高めるサポートを提供しております。本稿がワーキング・ホリデー滞在者およびその雇用を検討する企業の双方にとって、客観的かつ有用な情報源となることを願っております。